「岸田國士戦争劇集」初日ソワレ(白組)と8日目ソワレ(赤組)を観た(7月8日 金曜 19:00,13日 水曜 19:00/アトリエ春風舎)。

岸田國士の『動員挿話』と『かへらじと』は十数年前に作品論を書いたことがある*1。『動員挿話』の上演は何度か見た。というか、新国立劇場の上演(2007)が論文執筆のきっかけだった。が、『かへらじと』はほぼ上演された形跡がなく*2、今回、舞台を目の当たりにした感慨は一入で、岸田國士が書いた科白の美しさ、作劇の見事さに今更ながら舌を巻いた。それを感じさせる上演だったということ。以下は、例によって、だらだらとメモする。
構成・演出:谷 賢一(DULL-COLORED POP)/『動員挿話』(1927)『戦争指導者』(1943)『かへらじと』(1943)/演出助手:刈屋佑梨、石井泉/美術:濱崎賢二/映像:松澤延拓(株式会社カタリズム)/映像助手:イノウエタケル/照明:緒方稔記(黒猿)/音響:佐藤こうじ( Sugar Sound)/衣裳:友好まり子/所作指導:石原舞子/制作:DULL-COLORED POP/協力:アゴラ企画、アトリエ春風舎/助成:公益財団法人セゾン文化財団、文化庁「ARTS for the future! 2」補助対象事業
白組(7/8金)『動員挿話』『かへらじと』:倉橋愛実(DULL-COLORED POP)、荒川大三朗、石川湖太朗(サルメカンパニー)、石田迪子、伊藤麗、函波窓(ヒノカサの虜)、國崎史人、古河耕史/『戦争指導者』:古河耕史、荒川大三朗
赤組(7/13水)『動員挿話』『かへらじと』:阿久津京介、東谷英人(以上DULL-COLORED POP)、越前屋由隆、齊藤由佳、原田理央(柿喰う客)、ふじおあつや、松戸デイモン、渡辺菜花/『戦争指導者』:東谷英人、越前屋由隆
[声の出演]『かへらじと』、ラジオドラマ『空の悪魔』(1933)後者は7/15より有料配信:石井泉、小野耀大、小幡貴史、勝沼優、椎名一浩、田中リュウ、服部大成、間瀬英正、溝渕俊介、宮部大駿
舞台には一段高い板の間が作られ、正面奥の〝壁〟は縄のれんのように出入り自由。正面の欄間と横木は鳥居を思わせる形状。この板の間が『動員挿話』第1幕では宇治少佐の居間、第2幕は馬丁友吉夫妻の部屋となり、後半の『かへらじと』第1幕では神社の拝殿(原作では「拝殿は見え」ず境内の広場が舞台)や境内となり、第2幕は志岐行一の家の「奥の間」となる。
戦時のニュース映画風に、黒船来航(不平等条約)を起点とした日本近現代史と岸田國士(1890-1954)の主要年譜が、当時の映像等を交えて映写される。1904(明治37)年の日露開戦では、軍人に扮した役者が登場する。岸田の父だろう。この年は『動員挿話』の設定年で、父の庄造は大隊長(少佐)として出征し、14歳の國士は名古屋地方幼年学校に入学している。軍靴の音が響くなか、やがて1927(昭和2)年『動員挿話』の発表年となる。…

【白組】プロローグで軍人に扮した古河耕史が宇治少佐として再登場。『動員挿話』が、父親の出征時(動員)のエピソード(挿話)に基づくことを理解させる仕掛けだ。第1幕。陸軍少佐に仕える馬丁友吉が戦争に行くことに、妻数代が強く反撥する。数代の言動は、1927年の当時、劇評家は少佐と共にアブノーマルと見なしたが、いま聞くとしごくまっとうに聞こえる。それが、文脈次第では非国民となるから恐ろしい。
幕切れの女中よしの「井戸です」の科白は弱め。その前に、身を投げたはずの数代がシモテからゆっくり歩み出て、中央手前で座る。その彼女を見ながら友吉の科白「やりやがったな…」。死んだ数代の再登場についてはあとで触れたい。
古河はインテリ軍人の趣き。石田迪子は少佐夫人の品格が見えた。二人の発話は無理に感情を込めず、むしろ言葉自体がおのずと感情を引っ張り出してくるのを待つようなあり方。そう感じた。一方、馬丁夫婦は声が大きくぶっきら棒でいわゆる現代的な印象。こうしたスタイルの違いは両者の身分差(主従関係)を考えると納得できる。
[右上の図版は1927年9月 帝国劇場の初演写真(『演芸画報』1927年10月号)上:大谷友右衛門の宇治少佐、河村菊江の夫人鈴子、阪東嘉好の従卒太田/下:村田嘉久子の妻数代、守田勘彌の馬丁友吉/宇野四郎 舞台監督(演出)、井上弘範 舞台装置]
「戦争指導者」(1943年4月)は知らなかった。「軍艦献納運動*3」をサポートするために書いたらしい。初出は、谷氏(プログラム)によれば、日本文学報国会の機関誌「日本学芸新聞」で、『辻小説集』に収録されている。313字というからショートショートか。流頭(ルーズベルト)=古河と茶散(チャーチル)=荒川のコントみたいな短い対話。漫才風にアドリブから始めた。平田オリザの『ヤルタ会談』を想起。数代が自死した深刻な幕切れ後のコミックリリーフとして効果的。
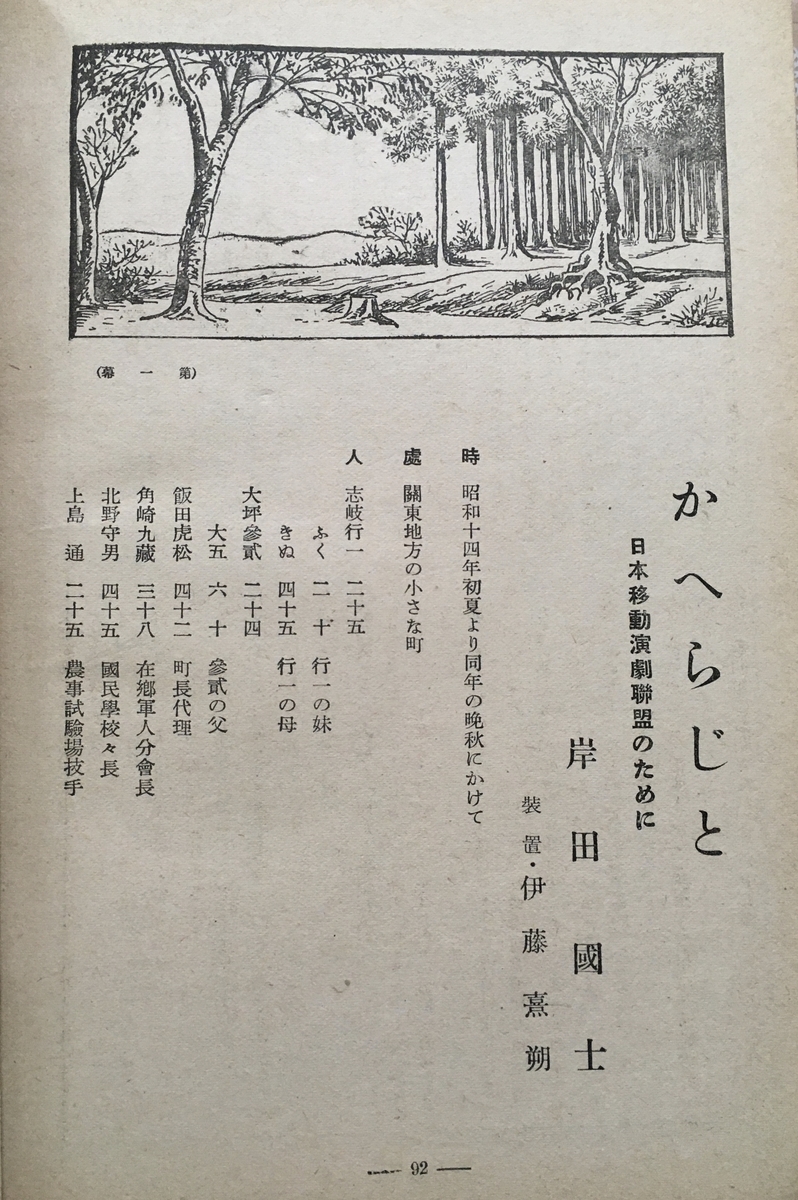
『かへらじと』は戦時の移動演劇用に書かれたため、それなりの人数が要る。アトリエ春風舎の小さな空間でコロナ下もあってか、第1幕の祭りの準備、第2幕の志岐の戦死報告会も、正面の〝縄のれん〟に映るシルエットや録音した声の出演などを駆使して対応した。姿の見えない役者と録音とのやりとりは、早朝の祭りの準備の情景としては少し物足りない気もしたが、主要人物の対話をフォーカスする利点もあった。赤紙の来た志岐行一は、親友の大坪参弍に、妹のふくを嫁に貰ってくれと打診するが、断られる。参弍は当初のイメージより少し年長の印象。
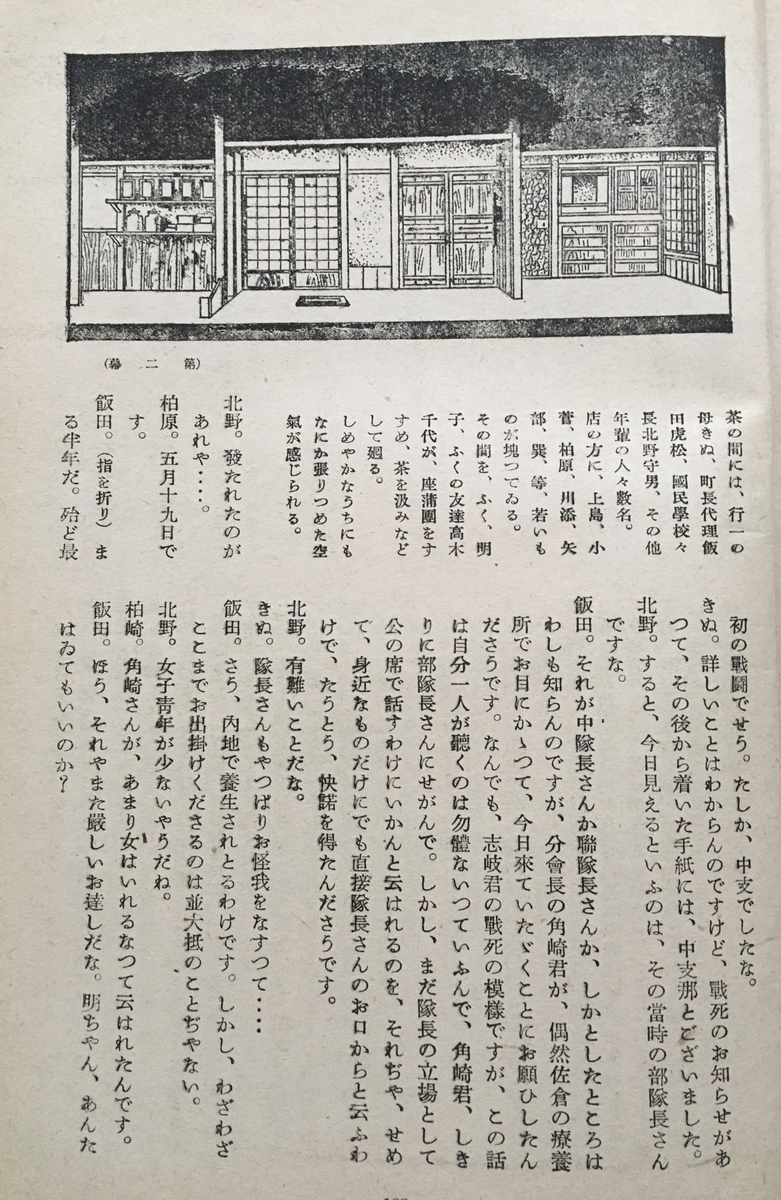
ハイライトは半年後の第2幕。戦死した志岐行一の遺影代わりに、本人が軍服に国旗の付いた銃を担いで鎮座する。死者の現前は『動員挿話』と同じ。女性らが座布団を敷き、湯飲みを置く。志岐が属した部隊の上級部隊長の副官 結城少佐が来行し、志岐の最期を語る場だ。結城少佐はもちろん古河。この語りが山場。小声で淡々と、ここぞのくだりは意を込める。うまい。語りのなか、戦場で志岐一等兵が部隊長に呼ばれて話しをする場面は、思わず見入った。部隊長役は大坪老人を演じる荒川大三朗。カミテの袖で着替えて登場するが、荒川の怒鳴る軍人造形はとてもリアルで迫力満点。一瞬、軍部が手を入れた改訂版かと錯覚した。オリジナルでそう感じるとは。新発見。[上記二つの図版は初出誌『中央公論』1943年6月号の伊藤熹朔による舞台美術のスケッチで、上左は第1幕、下右は第2幕。]
結城少佐は、この報告を次のように総括する。志岐の戦場での行動は、勇敢といえば勇敢だし、純粋といえば純粋だが、短慮無謀のきらいがあるため、全軍の模範とはいえないと。そうした留保を付けたうえで、少佐はいう、「われわれ軍人のみならず、日本人として、志岐君の一念には深く打たれるところがあることを、わたくし、率直にみなさまに申し上げたい」。生きては帰らぬ(かへらじと)決意は兵隊がみな胸に秘めてはいる。だが、志岐の場合は、すべてが例外に思われると。
個人的な過失を国家的な罪として自らこれを責め、友情をもって大義に結び、戦場に於いては、死にまさる奉公なしと観じた一徹素朴な精神を、わたくしは、涙なくして考えることはできないのであります。欲を云えばきりがありません。これが日本人です。日本男児です。謹んで志岐君の冥福を祈ります。終わり。
この「欲を云えばきりがありません」との科白はずっと耳に残った。当時(戦時)の日本では、これが岸田の絞り出したぎりぎりの「ヒューマニズム」であり、これ以上は残念ながら望めないと、岸田自身が言っているように聞こえたのだ。…
ラストのふくと参弍のエピソードはとても軽やかで明るい。大坪老人が、ふくの母親に娘を嫁にくれないかと言い出すが、肝心の参弍はもじもじして何も言えない。それに「まあ、こんなところかな」と大坪老人は言うのだが、これには思わず笑いが出た。岸田がこんな科白を書いていたかと、あとで確かめたほど。信時潔の賛美歌のような「海ゆかば」が流れて暗転。
古河を初めて見たのは『長い墓標の列』(2013 初日・中日)。次が福島三部作 第二部『1986年:メビウスの輪』(2019)、そして今回だが、相変わらずうまい。彼の存在で、舞台がグッと引き締まっていた。
数代の〝反戦〟を岸田國士の思想と捉えがちだが、それは違うと思う。岸田は劇作家として、血の通う生きた馬丁の妻を造形したら、結果として、戦後の憲法を有するわれわれが共感しうる〝反戦〟思想の人物像が創り出された。そういうことではないか。これは、イギリスの詩人キーツがシェイクスピアは「桁外れに所有していた」といったネガティヴ・ケイパビリティに関連していると思う(詳しくは先の論文に書いた)。
新国立劇場の深津篤史演出では、数代が不在の場面でも彼女を何度か舞台に現前させた。谷演出では、数代が自死したあと登場するが、おそらくそれは、友吉の最後の科白を彼女のからだに向けて吐かせるためと、続く『かへらじと』の第2幕で、戦死した志岐行一の遺影としてのからだにつなげるためではないか。『動員挿話』の演出で深津とも共通するのは、共に数代のからだを介し、観る者に考えさせる趣向だと思う(当時はともかく現代では共感しうる数代を通して、舞台を見/考えることを促す)。
岸田國士は戦争になったら勝たねばならぬと考えた。これは当時ではごく当たり前の考え方。それが〝悲惨な戦争(敗戦)〟体験を経て、日本はいまの〝平和憲法〟を得たのだが、それは人類の叡知(カント)であり、宝であるのかもしれない。
【赤組】機器のトラブルでプロローグのやり直しがあり、10分遅れでスタート。(開演前のスマホの注意や危機の操作もすべて谷氏だが、トラブル時のお詫びと弁明のお喋りには笑った)。
『動員挿話』宇治少佐はイメージより若く見えるが、声はよい。友吉は人物造形が優れている。立ち居振る舞い、科白。数代はちょっとアイドルタイプだが、役の〝過剰さ〟がよく生きられていた。女中よしも感じが出ていた。赤組は総じて現代的で感情を込めるあり方。よしの「奥さま、井戸…」はリアル。夫人がそれを聞いて出て行く様は、白赤ともにさほど切迫感がないのは演出か。友吉の、正面に現前する数代に向けられた「うそだよ、うそだよ、おれは行かないよ。行かないってばさ。ええい、うそだって云うのに、これでもわからんのか……」は、矢のように数代のからだを通って、われわれ観客に刺さった。
暗転し「戦争指導者」へ。早速 冒頭のトラブルをいじる二人。流頭=東谷英人、茶散=松戸デイモン

『かへらじと』2回目だけに科白がよく聞けるし、状況もよく分かる。志岐らしくマッチョでないタイプの役者。志岐行一と大坪参弍の対話はやや感情過多だが、「戦争志願奨励劇」(渡邊一民)としてリアルともいえる。第2幕の結城少佐は東谷英人。うまい。白組の部隊長は凄い迫力で改訂版かと思ったが、赤組は、声が知的な部隊長(越前屋由隆)ゆえ岸田のオリジナルと納得。[左図版の中段は 1943年6月 邦楽座(丸の内ピカデリー)で「移動演劇東京特別公演」として上演された『かへらじと』(軍部による改訂版)第2幕の舞台写真。佐々木孝丸演出、伊藤熹朔 装置、松竹国民移動劇団(ふく役は北林谷栄)出演/図版中の上段写真は同時上演の久藤達郎作『たらちね海』(『移動演劇図誌』1943年11月)]
本作は、要するに、赤紙が来てギョッとし、喧嘩の仲裁ばかりしていた青年が過って片目を失明させた親友の代わりに、その意志に報いるために死を賭して戦い、戦死する。国家(昨今よく聞く「国益」)や天皇陛下のためではなく、個人として親友のために生命を賭けた点がポイント*4。いまの日本では(特に若い人には)この点が見落とされるかもしれない。もし今回のオリジナルと改訂版(認可脚本)とを交互に上演できたら、岸田がいかに苦心して戦時の日本社会に受け入れ可能な伝統的「死生観」の枠内で、志岐行一の死なせ方を〝日本固有のヒューマニズム〟たりうるものにしようとしたか、また、いかに当時の軍部がいびつで狂信的で没理性的だったか、よく分かるのではないか(谷さんでも誰でも、上演してくれるなら、「認可脚本」は喜んで提供します)。
戦争前の1927年『動員挿話』で〝反戦〟だった岸田が、戦時の 1943年『かへらじと』で戦争を肯定する戦争劇を書いた? そうではない。軍人の家に生まれ、自らも軍人を目指した岸田國士は、反戦思想を抱いたことなど一度もなかったはず。『動員挿話』での〝反戦〟の位相については上記の通り。では、16年後の『かへらじと』で、岸田は何をしようとしたのか。
戦争は決して負けてはいけない。いったん戦争が始まったら理屈抜きに「お互いの生命を守り合うのが当然だ」(リレー評論「文学者と愛国心」1936)。だが、人命をモノのように軽く扱い、人間性の無視が蔓延している事態こそ「結局いざという場合に、国民の本当の力を出し切ることのできない最大原因」である(「文芸雑記」1940)。そこで、〝生命を大事にせよ〟〝国家より個人を尊重せよ〟との価値観を絶妙に盛り込んだ「戦争志願奨励劇」を書き、移動演劇として上演することで、国民を啓蒙しようとした。あくまでも、戦争に勝つための文化の「側衛的任務」として(「文芸の側衛的任務」1940)。
だが、そんな岸田の「戦争劇」も、そのまま上演されることはなく、舞台化されたのは、軍部の意向に沿って無残に改竄(改訂)された「認可脚本」だった。
*1:「戦争文化論(Ⅲ)——岸田國士『動員挿話』における〝反戦〟の位相」桜文論叢第68巻,2007/「岸田國士の戦争劇——『かへらじと』の認可脚本をめぐって」2009。
*2:谷賢一氏によれば、文学座研修科の発表会(2020年/鵜山仁 演出/文学座アトリエ)でやったらしい。
*3:「軍艦献納」といえば、「古典」という語の由来を想起させる。「古典」はラテン語の形容詞 classicus にから来ているが、これは「艦隊」の意味を持つ名詞 classis から派生した。つまり、classicus は国家の危機に、国家のために艦隊を寄附できる富裕階級を指し、転じて「人間の心の危機において本当に精神の力を与えてくれるような書物のことをクラシクスというようになり、さらに「絵画でも音楽でも演劇でも精神に偉大な力を与える芸術を、一般にクラシクスと呼ぶようになった」(今道友信)。ちなみに、prole は子供のことで、形容詞 proletarius は、そうした危機に自分の子供しか差し出せない貧しい人々を意味し、それがドイツ語のプロレタリアート(労働者階級)となって世界中に広がった。
*4:1938年に「国家を裏切るか友を裏切るかと迫られたときには、国家を裏切る勇気を持ちたいと思う。こんな選択をすれば現代の読者は憤慨して即座にその愛国的な手を電話にのばし、警察に通報するかもしれない」(小野寺健訳)と書いた E. M. フォースターの言葉と比較してもよい。